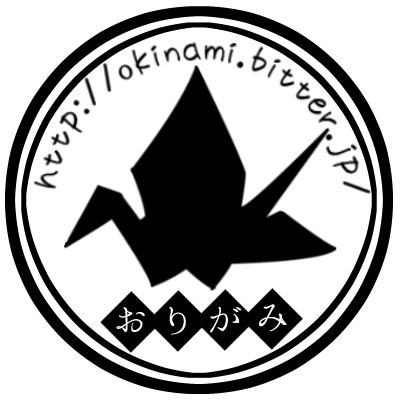
シュールストレミング異臭騒動
五月五日は真選組鬼の副長の誕生日だ。理由がなくともなにかと理由をつけて飲むのが男の集団というもの。理由があればなおのこと飲みの席が設けられる。急な出動に備えて多少酒を入れないメンバーを残して、あとはベロンベロンに酔い潰れていく。
上座についてる土方が、代わる代わるお酌を受けてるのを横目でみつつ、沖田は愛飲している鬼嫁を煽った。ひたすら腹に酒を入れて人の話をうんうんと聞くのが沖田の飲みの席でのスタイルだったが、ふと思い出したことがあって山崎を自分の横に呼びつけた。
「そういやザキ、忍者免許持ってるんで?」
突然沖田にそう言われて山崎は面食らったが、以前別の飲みの席で忍者の教習所の話をしていたことを思い出す。
「あー、取ろうと思って教習所まで行ったんですけどやめたんですよね」
「なんでィ、クナイの投げ方教えて貰おうかと思ったのに使えねぇなぁ」
沖田はあからさまにガッカリしながら、山崎に向かってシュッっとクナイを投げる真似をした。その手に本物が握られていたら、おそらく眉間にヒットしていたことだろう。
使えないと言われたとこに若干の苛立ちを感じつつも、山崎は驚きの気持ちが優った。
「沖田隊長柔軟というか、なんでも覚えますよね」
真選組幹部はほとんどが近藤の道場で知り合った旧知の仲だった。しかし近藤と出会う前に別の剣術を学んだり、独学でクセがついているものがほとんどでもあった。近藤の流派を正式に納めている者は少なく、沖田が一番手本に近い。そのため沖田の剣術は近藤と似た型だったのだが、江戸に来てから新しく伊東たちが使っている流派でもいつのまにか免許皆伝を納めていた。そしてそれは剣術にとどまらない。
「真選組で一番剣の腕がいいのにバズーカも使うし、爆弾も使うし、この間は原田に槍術も習ってましたよね」
沖田は天賦の才と努力で真選組の誰よりも腕が立つ。ならば剣だけを磨けばいいと思うのに彼はそうしない。仕事はサボっても鍛錬はサボらず、時間さえあれば新しいものも貪欲に学んでいた。副長の席を空けて昇進するためと言いつつ、宇宙毒物劇物取扱免許をいつのまにか取得していたのには山崎もビックリした。主に土方へ「死なない程度に嫌がらせをする」という活用をしているが、潜入中に入手した薬物などの調査で山崎も既に何度かお世話になっている。
剣だけにとどまらないのはなぜかと、その理由を沖田に聞くものは多かった。大体が「自分が納めた技術は敵として対峙したときに、どう攻撃がくるのか分かりやすいから」といった当たり障りのない回答しか返ってこない。
しかしこの日は酒で口が軽かったのか、はたまた相手が山崎だったからなのかはわからないが沖田が珍しく口を滑らした。
「俺たちの流派は剣道を主とした総合武術ってのもあるけど、まあ俺のはただの憧れでィ」
「憧れ……?」
沖田は手に持っていた鬼嫁を瓶ごと煽ってから答える。
「多分俺の初恋の人。すごく強かったんでィ……あ、この話誰にも話してねェから近藤さんと土方さんにも内密に」
「はぃぃぃぃぃひぃぃぃ!?」
山崎が驚愕の声を上げた瞬間に土方が山崎の隣に座ったものだから、驚きの声は悲鳴に変わった。
「なんで主役がここにいるんですか、早く上座に戻ってくだせェ」
「その上座でいくら待っても挨拶に来ない部下がいたんで、こっちから出向いたんだよ」
沖田を睨みつけた土方だったが、他人事のように答えた。
「なんでィ、ザキのせいじゃねぇか」
「俺はもう挨拶しましたよ」
「オメェだよオメェ」
二人に揃って言われて沖田は驚きの表情を浮かべた。どうやら本気で自分ではないと思っていたようだ。
「えぇ……俺はもう朝イチに祝ってやったんでいいじゃねェですか」
「もしかして寝てるところを、いきなり切りつけられたこと言ってる!?」
「へぃ。副長業がお忙しい土方さんに、安らぎのひとときをプレゼントしようかと」
「ひとときっていうか人生終わりそうだったんだけどぉ!? あとせめてお互い服着てるときにしろよ! 俺もお前も駆けつけてくれた奴もみんな気まずいだろ!」
山崎を挟んで二人の痴話喧嘩が始まってしまった。緊急事態かと思って駆けつけた隊士が朝チュンに居合わせたのも事故だが、それを隊士が揃ってるこの場で叫ぶのも事故に近い。山崎はそっとその場を離れて無関係を貫いた。山崎が立ち去ったのを確認してから土方はボソッとつぶやく。
「テメェに初恋があったなんて初耳だったよ」
沖田はキョトンとしてから破顔した。
「アンタ自分はあんだけ浮名を流しておいて、俺の初恋が自分じゃなかったのが許せないとは言いやせんよね?」
「そうじゃねぇよ。俺と会ったときにはもう近藤さん一色だったから意外だったんだよ」
「土方さんと会う前でしたからねィ」
詳しくは話したくない沖田は話題を切るように立ち上がった。
「部屋戻るのか?」
「へぃ、誰かさんが昨日なかなか寝かせてくれなかったんで、クタクタなんでさァ」
仕事中昼寝してたくせによく言うよと思ったが、口にはしなかった。数歩歩いたところで沖田は振り返る。
「あ、そうだ土方さんこれどうぞ」
彼は土方の顔面に向かって、懐から出した物体をスパーキングしようとした。間一髪でそれを受け止めた土方は眉間に皺を寄せる。
「あっぶねぇな、なんだよ」
「誕生日プレゼントでさァ。あんた今日はマヨネーズばっかり貰ってるから、マヨに合う缶詰見繕ってきやした」
顔を合わせた隊士から示し合わせたようにマヨネーズをプレゼントされていたし、この飲みの席でもいくつも貰っている。マヨネーズだけでも酒の肴になり得るが、つまみが増えるのはありがたい。
「へぇ、気がきくじゃねぇか。……ちょっとまて、これ毒でもはいってるのか?」
「それも捨てがたいですが、食べ物では遊ぶなって姉上の言いつけなんで」
「嘘つけお前この間マヨネーズに毒盛っただろ」
土方の言葉に沖田はげんなりとして答える。
「土方さん、マヨネーズは食べ物じゃなくて調味料です」
姉の言いつけはギリギリ破っていないという見解でいる。そしてケーキにタバスコを入れたりするのは、姉直伝の美味しい食べ方なのでそれこそ問題はない。土方も追及するつもりはないのか話はそこで切った。
「……まあありがとな、総悟」
沖田は振り返らずに片手を振って、今度こそ大広間を出て行った。
土方は自席に戻って新品のマヨネーズの袋を破る。
「ん? どうしたんだトシ」
「総悟がアテを寄越したんだ」
わざわざマヨネーズに合うと言っていたくらいなのだから、食べないわけにいかない。土方は早速缶詰を開封した。瞬間、開封した隙間から飛び出た液体と匂いに、部屋中の隊士が立ち上がった。
「もしかしてこれ毒ガスですか!? 局長、副長、退避してください!」
「ちょ、これ……総悟ぉぉぉ!!」
土方十四郎の誕生日の夜は、シュールストレミング異臭騒動で幕を閉じたのである。
◇
沖田はあの人との出会いについて初恋と言ったが、それが恋だったのかどうかは今となっては誰にも分からない。沖田がその相手に会ったのは一度きりだったし、相手は沖田のことなど気にも留めていなかっただろう。
近藤と出会って剣術を学び、土方が入門する前の出来事だった。神童だともてはやされた子にありがちな失敗を、一度だけ沖田もやってしまったことがあったのだ。
沖田にとって近藤が師であり初めての友である。つまりそれまで沖田には友達が居なかった。正確には友達になりたいと思えるような相手がいなかったのだ。親がいない沖田を蔑む者、姉にべったりなことを揶揄う者、はたまた「親がいなくてかわいそうな男の子と遊んであげる」とどこか上から目線の者。
一番厄介だったのが最後のケースだ。どこぞの箱入り娘が一人で遊んでいた沖田を、ひとめで気に入りひどく食い下がってきた。
「かわいそうだから私が遊んであげるって言ってるのに!」
断られるなんて頭になかった彼女はしつこくそう言って、最後は無理矢理沖田を連れて行こうとしたのだ。
ビックリした沖田はほとんど無意識に抵抗をした。この頃は道場で大人に混じって鍛錬を重ねていたため同年代の、それも箱入りの女児への力加減を知らなかった。力いっぱい振り払ったところ、彼女はあっけなく沖田から離れた。が、その反動で近くの植え込みまで吹き飛ばされて行ってしまった。
「きゃぁぁぁ!」
甲高い声は彼女のものだったのか、彼女の母親のものだったのか。放心していた沖田には分からなかった。とにかくその後は大騒ぎで女児は病院へ運ばれて、右腕に五針ほど縫う怪我をした。顔でなかっただけ不幸中の幸いだったが、残る傷だった。彼女と彼女の家族に必死で頭を下げる姉の横で、沖田もまた呆然と頭を下げていた。
しかし話がそこで終わればよかったのだが、そうは行かなかった。娘を傷つけたことがどうしても納得行かなかったその親が、一応和解したにも関わらず沖田を攫った。沖田が年の子相応に怯えたり泣いたりしたら溜飲が下がったのかもしれないが、彼は凛としていた。自分自身に原因があるため抵抗もしなかった。また怪我をさせて姉に頭を下げさせ、悲しませたくなかったのだ。ついに痺れを切らした親は、ゴロツキに金を握らせて沖田を痛めつけることにした。
彼らは沖田を神社の裏に引き連れ、十人ほどで殴る蹴るの暴行を行った。流石にやばいと気がついたときには手遅れだ。人気のない場所で、大人数相手。しかも人を痛めつけるのに慣れた彼らは、真っ先に沖田の両手を拘束して動きを封じた。縛り付けながら大人だったら折ってた、折られないだけ温情だと笑っていた。丸太のように転がされているうちに、頭を強く打って沖田の視界は霞んでくる。腕が折れてなくても死んだら意味ないじゃないか――沖田は朦朧としながらそう思った。死んだら姉を悲しませてしまう。でも子守りから解放されていいのかもしれない。そんなことを考えていたところでゴロツキたちとは違う男の声が聴こえてきた。
「あー、嫌なもの見ちまったじゃねぇか」
男は沖田がボコボコにされているのを、見て見ぬ振りできないようだった。一人で集団相手に乗り込んでくるとは無謀だとしか言いようがないが。
「俺も真っ当に生きてるわけじゃねぇが、こんなガキ相手によってたかって恥ずかしくねぇの?」
「じゃあガキの代わりにお前からやってやるよ」
沖田を囲んでいた奴らが一斉に男に向かっていく。うつ伏せの状態で倒れた状態の沖田からは下半身しか見えないが、どうやら若い男だった。
「いっ……」
構わなくていいから逃げろと伝えたいが、声もろくに出なかった。自業自得の沖田と違って無関係なのに。意識が遠のきそうになるのを堪えてみると、男は地面を蹴って土埃を先頭のゴロツキの顔面にふりかけ、怯んだ隙に木刀で強く打ち込んだ。倒れ込んだ相手を後続に向かって蹴飛ばして三人ほどドミノ倒し状態にする。後ろから襲いかかった相手には振り返りながら弁慶の泣き所を強く打ち付けた。その次の瞬間にはその横にいた男の急所を突いている。背中を木刀で攻撃されてしまい転んだと思えば、起き上がり際に石を拾ってそれを相手の頭に叩きつけた。
「……すげぇ」
近藤のように綺麗な剣術ではない。沖田が初めてみる喧嘩のための、どんな状況でも勝つことだけを考えた戦い方だった。
一人であっという間に全員に勝ってしまった。男はめんどくさいと言いたげに大きなため息をついて、沖田の側にきた。
「おいガキ、家はどこだ」
「――」
うまく喋れなかったが男はわかったと言って沖田を背負った。結局顔は見れないまま、沖田は男の背で意識を飛ばした。
気がついた時には自宅の布団の上で、心配した姉に介抱されていた。夢のような時間だった。結局助けてくれたのはどこの誰かわからず仕舞いだったが、沖田はその日以来剣道として平行して喧嘩に負けないための技法を身につけていった。近藤とは別の意味で憧れの人になっていた。
◇
土方の誕生日の翌朝、シュールストレミングの残り香で屯所は大騒ぎだった。非番だった沖田はこれ幸いと屯所を抜け出して川辺でたっぷりと新鮮な空気を味わっていた。
五月の過ごしやすい気温のおかげで川辺にはそこそこの人出があった。川で遊んでいる親子連れ、釣りをしている青年たち、恋人同士で会話を楽しんでいるもの。
「平和だなァ」
ぼんやりと行き交う人々を眺めていた沖田は、ふと違和感を覚えて川に入っていた一人の女性を見る。年齢は沖田と同じくらいで、見た限り一人だった。妙齢の女性が一人で川に入るものだろうか。探し物かなと思いつつも沖田訝しんでいると、女性は溜息をついて岸にあがってきた。非番だったため私服だったが顔を知られているのか、沖田を見て彼女は「あっ」と声をあげて近づいてきた。警察は警察でも沖田は幕府特別武装警察なので失せ物相談をされても困るのだが、こういったことはたまにある。邪険に扱って後日クレームが上がってきても事なので、沖田は大体話を聞いて簡単なことなら手伝い、難しい場合は交番に連絡したり、気が向いたら万事屋に仕事を斡旋している。
「どうしやしたか」
しぶしぶ声を掛けると、彼女は少しムッとした表情を浮かべた。
「わからないんですか?」
「……川になにか落とし物をしたんだなァってことくらいしか」
沖田が答えると、彼女は本格的に腹を立てたらしい。
「ええ落としました。貴方の顔写真付きの新聞の切り抜きを。……本人を見つけたのでもうそっちに用はありませんけど」
女は着物の右腕をめくって見せつけてくる。
「こっちはひと時だって忘れたことがないのに、忘れているだなんてあんまりじゃないですか」
右腕の傷には覚えがあった。丁度昨日の飲みの席で思い出したばかりの幼少期の失敗。
「忘れて、ないです。えっと……子供の時より綺麗になっていたので、すぐに分からなかっただけで……」
「……そう」
彼女は照れもせずに視線を斜めに落とした。
「……ここではなんですので、場所を移しませんか?」
意を決して話しかけて来た彼女の言葉に嫌な予感しかしなかった。しかし拒否権は沖田にはないも同然だ。
案内されたのは彼女が江戸で滞在している間使っている、旅籠に隣接した食堂だった。気は進まないが沖田は踏み込む際に携帯電話のサイドボタンを三回押し込んでから入店した。
二人で少し早めの昼食を取り、食後のお茶が提供されたタイミングでやっと彼女は本題に入った。
「私を傷物にした責任を取って結婚してください」
そっちのパターンで来たかと、沖田は頭を抱えた。沖田の新聞記事を見て来たということは、いつのものだか分からないが確実に真選組一番隊隊長と書かれた記事である。江戸の幕府お抱えの警察幹部だと知った彼女が、金の無心をしにはるばる江戸まで来たのであれば良いなと願っていた。当時慰謝料は姉が支払っていて、沖田は仕事を始めてから姉に返したが心の中で傷は確実に残っていた。彼女の両親からされた仕打ちを考えればどっちもどっちとも思えるが、幼かった彼女はそれには関与していない。このタイミングで金を渡せるのであればそれでもいいと思った。
「警察って言えば聞こえはいいですけど、要は将軍の駒でさァ。万が一の場合、家族ごと首が飛ぶ場合もありやして……」
腕の五針ほどの小さな傷では済まない。それを沖田は説明していったが彼女は納得していない。何度説明しても無理だったため、沖田は言い訳を変えた。本当に言いたくないことではあったのだが彼女には誠意を持って接しないといけないと思った。
「俺には良い人ってのがいやして……そいつとも結婚することは絶対にないんですけど、貴方のことを好きになれることはないんでさァ」
「そう、私を差し置いて自分は幸せを見つけたということね?」
逆効果だった。冷静に考えればそれもそうだ。沖田は致命的な判断ミスをした。調教できない、してはいけない女性相手をするのは難しく頭が回らない。
「結婚は無理ですけど、金なら――」
「もういいです」
そう言って彼女は手をあげた。それが合図だったのだろう。旅籠の奥からぞろぞろと帯刀した浪士たちが出てきてあっという間に沖田を囲んだ。
「金目当てだったらよかったのになァ」
「察しはいいのね。そう、攘夷派と手を組んだから真選組に潜り込みたかっただけよ」
弱味に付け込んだら可能性はあると思ったんだけど、と彼女は舌打ちをした。襲い掛かってきた浪士に、抜刀して反撃しようとしたところ、彼女がその間に割り込んできた。沖田は咄嗟に刀を引いた。その瞬間あっという間に浪士たちにとらわれてしまった。力だけの勝負では沖田に分はない上に体勢も悪かった。あっという間に沖田は頭を地面に押さえつけてしまう。
(考えろ、こんなときあの人なら――)
彼女が先ほどのように阻止してくる限り沖田は刀では戦えない。ひとまずこの窮地を脱することだけを考えようと、頭を押さえつけていた手に噛みついて、足元に居た男の股間をけり上げて抜け出そうとしたが、すぐに別の複数人で押さえつけられて失敗に終わった。
しかしこんな場所で、まだ諦めるわけにはいかない。どうしたものかと悩んでいると入口の方から「今日は貸し切りだ」と声が聞こえた。見張り役の浪士たちが誰かの入店を拒んだのだろう。しかし相手は一般人ではなかった。よく知った声で「御用改めだ」と聞こえた。入店の際に沖田がしたサイドボタンの三回のプッシュ。あれは土方に向けた緊急通報であり、位置情報を送信するシステムだ。
てっきり何名か隊士を引き連れてくると思ったのに、現れたのは土方ひとりだった。
「土方さん、その女は……」
沖田が叫んだが口を塞がれて全部を伝えることができなかった。しかし沖田が不覚を取っていることで状況を把握したようだ。
「……なるほど女は一般人か」
言いながら土方は抜刀した。浪士に切りかかると同時に、沖田がされたのと同じように女がかばおうとした。土方は笑いながら刀の軌道を変えた。机を叩ききり、ひるんだ女にテーブルに置いてあった胡椒をぶちまける。そのまま女を床に倒したと思えば、近くにあった椅子を被せて拘束、その椅子の上に立って寄ってくる浪士を次々と切り倒していった。鮮やかな手腕だった。それを目の当たりにして、沖田は信じられないことに気が付いてしまう。
(まさか、そんなことって……)
でも何度見てもその戦い方に見覚えがあったのだ。
「二回も同じ女にやられてるんじゃねぇぞ、総悟」
土方は沖田を見て不敵に笑った。
「……っ、最悪!!」
沖田が憧れそして初恋だと思っていた人は現在の恋人だったのだ。近藤から話は聞いていたが、沖田はバラガキ時代の土方を直接みたことがなかった。だから気が付かなかったというのに、口ぶりからして土方はすべて知っていたのだ。
沖田は怒りのままに自分を拘束していた浪士を振り落して、土方と共に切り刻んでいった。
「……俺の初恋は『バラガキのトシ』であってアンタじゃないですぜィ」
「どっちも俺だよバーカ」
◇
「そういや土方さん、なんで一人で来たんです?」
浪士を全員倒したあと、女に手錠を掛けながら沖田が聞く。すると土方は片眉をあげて怒鳴りつけた。
「どっかのドSバカがぶちまけた異臭のおかげで、屯所に残ってる連中が居なかったんだよ!」
「ぶちまけた実行犯は土方さんでさァ……ってことはもしかしてここの後始末って……」
「頭がカラでもそれは察しがつくんだなぁ? 全部お前の仕事だよ、総悟」
一難去ってまた一難。心身ともに疲れたところにトドメを刺された心持だった。
「俺ァ非番なんですけどねィ」
「全部自分で蒔いた種だろ。……ほら、手伝ってやるから」
最後の最後で土方は沖田に甘かった。しかし沖田はまだ不服だった。
「あーあ、やっぱり缶詰じゃなくて安らぎをプレゼントすればよかったでさァ」
そんなことを思っても、もう後の祭り。