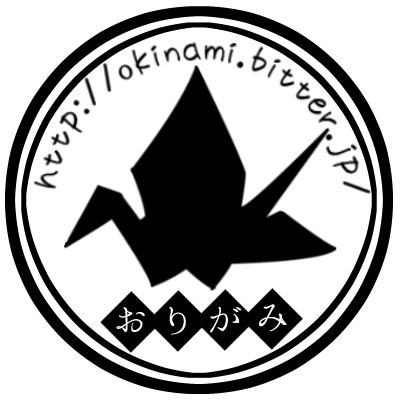
聖痕
沖田総悟には真選組一番隊隊長に就任するときに近藤と取り交わした約束があった。
特攻隊長としての危険手当は要らないがその代わりに殉職した際には毎月姉に仕送りをして欲しいという、近藤や土方からすれば頼まれるまでもないようなことだった。
しかしその約束こそが総悟にとっての覚悟でもあった。
「心にかかるもんがあったら真っすぐに刀が振るえないでさァ」
何が何でも生き残るという気持ちは捨てた。まだ十代の子供が。真選組設立時点で最年少の子が。
その総悟の姉であるミツバが死んだ。弟を残して。
近藤のためなら鬼にでも人殺しにでもなれる子が、近藤の隣以外に帰る場所がない子になってしまった。
土方はミツバを失った総悟がいよいよ心残りなく戦いの中で死んでしまうつもりなのではないかと思ったこともあった。でも総悟は強く、誰にも負けない。だからどんな争いの中でも生き残っていった。
――人殺し。
――人殺しの目をしている。
たびたびそう呼称されるようになった彼が、私欲のために人を殺めたことはない。力をひけらかすこともなく、市民を守り、部下をも守る。だが好戦的であり、強者との真剣勝負を好む節もある。
「大切なら気をつけてやって。あの子、危ういよ」
土方にそう忠告したのは万事屋だった。伊東とのたった一人で近藤を護るために同じ制服を着た仲間を文字通り切り捨てたあの後だ。
「末恐ろしいガキだよ、本当」
沖田総悟は強かった。銀時のように戦場で独り生き残るためでも、信女のように人殺しの道具として育てられたわけでも、神威や神楽のように戦闘種族でもなかったのに。
「近藤」のためならどこまでも強くなれるし、顔馴染みを殺すこともできた。裏切ったとはいえ、数時間前まで同じ釜の飯を食っていた相手を。剣の腕だけでは生き残れない状況だったのだ。躊躇いなく粛正できる心の強さがなければ。
それでも真っ直ぐ近藤を見て、近藤の元で市民を守る。その芯があるうちは大丈夫だ。しかし銀時は知っている。大切なものが、守りたかったものが、一瞬で消えてしまうことがあることを。「人」を自身の芯にしてしまった者の危うさを。だからこそ土方に忠告した。
銀時の忠告は徐々に形になって現れ始め、総悟はついになんの躊躇もなく魔剣マガナギを己の心臓に突き立てた。
あの瞬間、総悟はすぐ近くにいる近藤のことなど忘れていただろう。もしあれで何かあったとき、最終的に焚き付けたことを泣いて後悔するであろう大将のことを。真選組一番の戦力を失うことがどういうことかを。
――もう近藤さんじゃ留めておけねぇんだな。
土方はその後、真選組のために、総悟のために。そう理由をつけて自分自身のためだけに総悟を抱いた。どこにも行くなと願いを込めて。幸か不幸か彼は土方の腕の中に収まり、生涯抜け出すことはなかった。
◇
どういう因果なのか人殺しの必要がない世界に、人殺したちは生まれ変わってしまった。
沖田総悟は生まれ変わって数年後から、徐々に前世のことを思い出していった。前世の年齢の出来事と現世の年齢に合わせて思い出しているのか、育てば育つほど記憶は増えていく。
前世でそうしたように剣道を学びたいとねだって道場に通ったら近藤とも再会できた。これはもしやと思っていると予想通り土方が、原田が、集まってくる。
現世でまたつるむとなると側からみて不思議な関係ではあったが、楽しかった。
道場に通いつつ学生をする生活をしながら、総悟は高校三年の七月、誕生日を迎えて十八歳になった。
かつての姉が心配していたように常に大人の中で生きていた総悟にとって、同年代と学校生活を送るのはとても苦痛だった。しかも精神年齢はともかく、人生二週目ともなると確実に「人生経験」は跳ね上がる。
せめて共有できる仲間が身近にも居ればよかったのだが、学校にいる前世の知り合いは先生に一人だけ。バドミントン部とカバディ同好会を掛け持ちで顧問をしている山崎がいるだけだった。
「つまんねぇなァ」
授業はもちろんだが部活もだった。幼少期から剣道をしていた総悟は全国レベルで有名だった。高校こそは全く関係ない部活に入ろうと思っていたのにも関わらず、入学早々に捕まってしまい結局剣道部に所属してしまった。
たまに外部のプロが教えてくれる他は素人の顧問がいるだけの部活だ。既に免許皆伝の総悟が入部しただけで部員の目の色が変わる。総悟に取っては何の身にもならない時間ではあったが、それでも教えを請われれば「隊長」と呼ばれ剣術指南していた頃の記憶が蘇り、ついつい本気で指導してしまい試合でも部全体で結果は良い。
学校と部活が終わった後の金曜日。七月の体育館で剣道部の練習をして汗だくになった総悟はいったん家に帰りシャワーをすます。冷凍庫のチューパットを咥えながら鞄の中身を減らして「近所のお兄ちゃん」こと土方の家に向かった。土方は近藤の剣道場で知り合った今の言葉で言うなら幼馴染だった。実家は近所では名のある家で、しかも今は警察で仕事をしているため年の離れた一人暮らしの家に度々入り浸って泊っても親には全く不信に思われることはなかった。
貰っていた合鍵で家に上がり、ソファとローテーブルの間に腰かけて教科書を広げた。勉強は好きではないが、高校三年でもうすぐ夏休み。いよいよ受験モードに切り替わるタイミングだった。
取り急ぎ一通りの宿題を片づけてから、世界史の参考書を引っ張り出したところで家主が帰ってくる。
「もう来てたのか」
「ん、お帰りなせェ」
土方は鞄をおいてスーパーのビニール袋から冷蔵庫に中身を移したあと、ペットボトルと煙草だけ持って総悟の近くまでくる。
「受験勉強か……ここで勉強するならそろそろダイニングテーブルでも買うか?」
一人暮らしの土方の家には必要最小限の家具しかないため、椅子もなければ大きなテーブルもない。総悟が入り浸っていても、男二人で食事をする程度ならローテーブルでも事足りていた。
「大会終わったら部活も引退なんで、そしたら自宅で勉強しやす」
今は総悟の帰りが大きな事件などない通常時の土方の帰りの時間と近いのでちょっとの時間潰しのためにここで勉強しているだけだ。部活がなくなったら流石に時間を持て余す。
「でもお前、予備校行かないなら俺が見てやるよ」
土方がそう言うと総悟はあからさまに嫌そうな顔をする。
「アンタに見てもらったら近藤さんとところ行く時間無くなりそうで嫌でさァ」
「おいこら、そんなに成績悪いのかよ」
少し焦った表情の土方を無視して総悟は話し続ける。
「剣道も部活なんかじゃなくて近藤さんの道場がいいのになァ。近藤さんがいねぇんじゃつまんねぇや」
そういうと、土方は眉間に皺を寄せて彼の頭を軽くはたく。総悟の横に座ってから、煙草に火をつけた。
「成績微妙なんだから、内申点のためにも部活は最後まで続けとけ。どうせあとちょっとなんだし」
総悟の成績はムラが多い。体育と科学とだけが突き抜けて良くて、数学が上位。それ以外は下から数えた方が早いものすらある。
科学ができるなら他の教科もできるだろうと土方が詰めたこともあったが、総悟は「土方さんのために宇宙毒物劇物取扱免許持ってやしたからねェ」の一言で片づけた。恐らく頭は悪くないのだ。興味がないことに記憶領域が割り当てられていないだけで。
今生では警察にならず、実家の道場を継いだ近藤の元で再会したいわゆる武州組は相変わらずだ。総悟以外は皆もう社会人なので週に二回の稽古の後たまに飲んで帰ったりする程度だが誰一人変わっていない。今生でも仲間であり家族だった。総悟も道場に通ってはいるが、中学に入ったタイミングで部活を優先するようにと道場主の近藤から言われてしまっていた。総悟の現世での人間関係が希薄にならないようにという近藤の気遣いだ。
「大学は決めたのか?」
「いくつか候補はありやすけど。……土方さんと同じところとか」
「ふーん。学部は?」
「……法学部」
総悟の得意科目からはかけ離れていて、予想すらしていなかった土方は口に加えていた煙草を手に移した。
「なんでまたそんな難しいところに。近藤さんに誘われてるんだろ?」
とりあえず視野を広げるためにも大学には行って、そのあと総悟が望めば一緒に道場で働いてもいいと近藤は言っていた。総悟は剣の天才だったが教えるのも以外と上手い。本人は調教だなんだと軽口を言ってはいたが、剣の前では真剣だった。だからこそ誰かの下にいるくらいがちょうどいいと文句をいいつつも部活でも部長としてしっかり後輩を導いていた。
そんな総悟だからこそ、当然近藤の話を呑むと土方は思っていたのだ。しかしとりあえず行くだけの大学の選択肢に法学部を選ぶというのはまずないだろう。
「確かに近藤さんといるのも捨てがたいんですが、今は近藤さんを近くで守る必要もないですし。それを抜きにすると、アンタと警察やってんのも案外悪くはなかったんです」
「は……?」
思いもよらなかった言葉に土方はまた驚く。じわじわと煙草の灰が指へと向かってくるので吸うことを諦め、それを灰皿に押し付けてから総悟に向き合う。
「警察に?」
たっぷりと時間をかけたのに月並みな質問しか出なかった。それに対して総悟は「考え中」とすぐに言い切る。
「この世界だと配属先が土方さんの部下になれるとも限らないし、そしたら意味ないなって」
「お前が来る頃までに俺が人事に口出せるようになってればいいんだな?」
「できるんで?」
総悟の言葉に土方はかつてを思い出させるような不敵な笑みを浮かべた。
「何が何でもやってやるよ。というかそういうことならなおさら勉強やっとけ。最短で来い」
土方が買ってきた材料で総悟が簡単に夕食を作って先程まで勉強していたテーブルへと運ぶ。
食事と一対一の割合でマヨネーズをしぼりながら土方はやっぱり、と言い出す。
「今後テーブルは要るよな。そろそろ買うか」
先程終わったと思った話を蒸し返されて総悟は呆れて答える。
「要らないですって。だいたいどこに置くんです」
今使っているローテーブルとソファを捨てるにしても、ベッドで部屋の大部分は埋まっている。当然の疑問だった。
「ちげーよ、まずはマンション買うかって言ってんだ」
「……はい?」
「お前が高校でたら一緒に住まねえか?」
あまりにも軽く言われて混乱する。総悟とてそれを望んだことは何度もあった。何せ前世では任務で離れているのを除けば誰よりも長くずっと一緒にいたのだ。だから一緒に住んでいないのが不自然であるような感覚すらする。
まだ返事をしていないのに断られると思っていないのか土方はどんどん話を進める。
「マンション買って、家具と家電も揃えて。……ペットも飼いてぇな」
「アンタかわいいもん好きですもんねェ。猫とか犬とか……俺とか」
深刻に考えてしまっているのを悟られないように総悟がわざと軽口を言うと、「自分で言うな」と土方は笑っていた。
食事が終わって総悟が食器を片付けていると土方が後ろから声をかけてくる。
「総悟、今日泊まってくだろ」
「ええと、うーん……」
明日は総悟も土方も休みだった。そういうときはきまって土方の家で話をしたりゲームをしたり食事をして、そのまま風呂を借りて泊まっていく。しかし先日十八の誕生日を越えてから総悟はそれができないでいる。土方が明確な意図を持って身体に触れてくるようになったのだ。
悩んでいる間にも土方は総悟を背後から抱きしめて首筋に口付けてくる。
皿を落としそうになって慌てて洗い物を中断して土方の方へ向き合う。
「ああああああ、そう、俺、今日あの日なんでできないです」
「あの日ってなんだよ、お前生理ないだろうが」
「便秘! 便秘なんでさァ」
「総悟」
セックスの誘いに気が付かないフリをしたり、理由をつけてかわしていたがもう限界だった。そもそも今までのもバレていたはずだ。土方が誤解して変に拗れるのも嫌だった総悟は観念して白状する。
「……だってあの頃とは違うやないですか」
現世での性行為の経験はなくとも、身体を開かれることが幸せで気持ちのいいことであることは知っている。怖いのは抱かれることではないのだ。
戦いはなくて、総悟の姉も現代医療の恩恵を受けて健康に生きてて、自分たちは鬼でも人殺しでもない。責任と重圧を背負った副長と一番隊隊長でもなく、二十四時間三百六十五日一緒だった時とは違ってお互い帰る家は別にあって、家族仲も悪くない。互いで互いを支えなければ生きていけなかったあの頃とは違う。近藤が捕われて、真選組が無くなって、そうなったらもう行く場所一つなかったあの時の二人とは。
総悟はそれでも今生でも土方が好きだった。だからこそ思うのだ。土方も前世と同じく今も姉のことを好きなのではと。自分にかまうのは土方が前世での出来事に引きずられて、縛り付けるように抱いたことに対して罪滅ぼしをしようとしているのではないかと。
「俺ァあの時あんたに求められて幸せでしたよ」
だから罪悪感など抱く必要などないのだ。そこまでは言わずともわかると信じて総悟は言わない。その代わりに解放の言葉を告げる。
「姉上とくっつけばいいやないですかィ。今はちゃんとした仕事してんやし」
同じ警察でも死ぬ可能性は極めて少なくなった。前世のように毎日死の淵に立っているようなことはない。勝てば官軍、負ければ賊軍みたいに立場が急転することもない。むしろ収入面で安定していて夫にしたい人も多いだろう。
なぜか姉には自分たちのように昔の記憶があるわけではなかったが、それでも土方のことを気にしているような節がある。土方もそれは気がついているはずだった。
「悪いがそれは無理だ総悟」
土方があの時ミツバの手を取らなかったのは愛だ。幸せになって欲しいという願いでもある。それは生まれ変わった今だって同じこと。しかし土方はそんな綺麗な愛とは別の感情を総悟に抱いている。
「俺はもう、お前が普通に所帯もって、普通にガキ作って、普通に生きたいと言っても離してやれねぇよ」
胸を焦がすようなこの想いは、ただの執着だった。
「なぁ総悟」
すがるような声だった。その声に、総悟はようやく観念した。
「……今日は泊まっていきやす。明日は物件探しですかねィ」
◇
クチュクチュとローションの音が響く。ドロドロとした液体が穴からあふれて落ちていく感覚を受けて、総悟はどれだけシーツを汚しても今は洗濯に困ることはなくてよかったと安堵した。前世では屯所にいる人の目が多すぎて苦労したのだ。
「よそごととは余裕だな?」
「へィ。誰かさんがビックリするほど優しいんで。生まれ変わったら性癖変わったんですかィ?」
「バカ、最初はちゃんとしたほうがいいだろ」
前は初めてでももう少し手荒だったと総悟思ったが、そもそもあれは繋げ止めるためであり土方も必死だったのだと思い出した。
お互いだけが支えだったあの頃とは違って、今度は愛し合って抱き合うのだ。普通の恋人のように、キスをして身体を撫でて、最後にたっぷり挿入して。
ふと総悟は気が付いて声をかける。
「そう言うアンタもなんか考えてやすね」
「ん、足……傷ねぇなと思って」
視線の先は土方の指が埋め込まれた後孔より先にある左の太ももだった。記憶が正しければそこにはかつて銃槍があった。
「なにせ平和な世界なんでね。なんもねェですぜ」
土方は右手を総悟の左胸に乗せた。性の匂いを感じさせない触り方だった。
その場所にも覚えがある。残るほどの大きな怪我を負うのはそこまで多くはなかったが、神威とやりあった時の傷は一番大きく残った。
「さみしいんですか?」
総悟はなんとなくそう感じた。
確かな腕と、絶対的な信頼があったから土方が自分だけを頼ってあの場に送り込んだ。その痕跡がごっそり消えてしまったのだ。
「違う、怖かった」
そう言って土方は総悟を抱きしめる。上に乗られてる状態なので重いが言い出せる雰囲気ではない。
「お前がここに怪我した時、別々に戦って思い知った」
動かせる手駒がなかったとはいえ、総悟が自分たちの近くにいれば将軍をもっと安全に護れたのに。何度かそう後悔したが、全て終わって蓋を開けてみれば総悟を空に送り込んでいなかったら姫も含めて全滅していたことを知った。
大怪我を負いながらも土方の命令をたった一人で遂行していたのだ。
自分の選択が正しかったのだと思うと同時に、九つも下の未成年にとんでもない役割を押し付けたことを知る。
どこにも行くなと抱いて縛り付けた本人が死地になるかもしれない場所へ送り込んでいるのだ。
総悟の消えない傷は土方の傷でもあった。何度も抱きながら、何度も触れた場所。その場所に土方は口付け、ジュっと音を立てながら強く吸う。
「……これ、数日もあれば消えますぜ」
「毎日付け直せば一生消えねぇよ」
「はっ……!?」
顔を真っ赤にさせた総悟が可愛くてもう一度抱き締めた。耳元でそっと囁く。
「なぁ……挿れていいか?」
返事はなかったが首が縦に動いた。
めりめりと身体を開かれるように押し進められたが痛みはそこまでなかった。ゆっくりと一番太いところが入ってそのあとは勢いよくねじ込まれた。
「ンっ……あっ、はぁ、ひじかたさん」
「総悟、全部入った」
「やっ、まだ動かねぇでくだせェ」
「んなこと言ってお前自分で動いてるだろ」
初めてだけど、身体は知らないのに心が知っている。動かないでと言ったのに総悟自身がゆるゆると腰を振っていた。それに合わせて土方も奥を突く。
「やだ、ヤダ、土方さん、土方さん!」
「痛……くはなさそうだな。気持ちいいか?」
「わかんねぇっ、……土方さんでお腹いっぱいになってやす……」
「……アホ」
煽るのをやめて欲しいと土方は切実に願った。大切に抱きたいのに我慢の限界だった。何せ総悟が十八になるまでずっと我慢していたのだ。
総悟は背中に回していた右手をほどいて土方の頬を撫でる。
「好きです、土方さん」
そこから先の記憶は正直ない。俺も好きだ、もう離さない。それだけを繰り返して気が付いたら総悟のナカに精を放っていた。
全てが終わると土方は汚れたものを全て処理してからベッドに腰掛け煙草に火をつける。寝たままの総悟は背中しか見えない。
「ねぇ、土方さん」
煙草を吸う背中に声をかけた。
「なんだ?」
振り向く気配を感じて総悟は背中に抱きついた。顔を見られたくなかったのだ。
「俺ァアンタに貰ったもんで嫌だったもんなんて……犬のエサ以外ありやせんでしたぜ」
信頼も、制服も、時間も、セックスも、傷跡さえも――。
土方はしばらく固まってから総悟の頭を撫でた。
「なんだオメェ、マヨごと愛せよそこは」
「それは無理な相談でさァ」
総悟は笑って、土方も笑った。幸せの跡がそこにはあった。