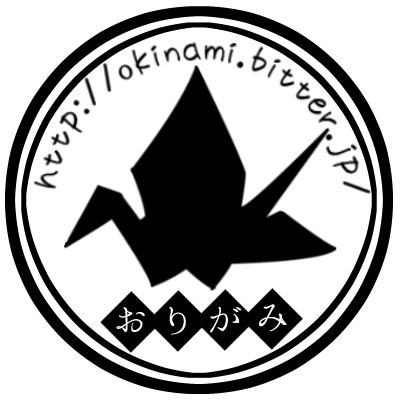
巡り合わせの愛3
江戸が落ち着いたあと迎える、最初のヒートの前日のことだ。
「一週間篭りきりになるから美味いもんでも食いにいくぞ」
と土方が沖田を連れ出した。今までは決まって「明日から仕事ができないから」と書類と睨めっこだったのに珍しいこともあるものだと沖田が思っていたら、当然のように裏があった。美味いものと言うのでてっきり土方スペシャルが食べられる行きつけか、はたまた会合で良く使う料亭かと沖田は思っていたがそのどちらでもなかった。タクシーに乗り込んではるばる高級ホテルまで来てしまった。
土方がタクシーの料金を支払うのを待ってから一緒に降りる。ホテルの入り口に横付けされていたためすぐにドアをくぐることになる。
土方が視線を走らせたところで、案内役のボーイが絶妙なタイミングで声をかけてくる。予約していた土方だと言うと「お待ちしておりました」とエレベーターまで案内してくれる。
沖田は慌てて袂を探った。奢ってもらうつもりで着いてきてしまったので持ち合わせがまるでない。土方はというと普段は持ち歩かないようなトランクを持っていて、そこそこ荷物が多い。
「土方さん、俺今日財布持ってきてないでさァ」
「知ってるよ。つーか俺がお前に出させたことねぇだろうが」
土方がいつも沖田に金を出させるつもりがないのはわかっていたが、それはせいぜい酒を飲んでも一万行かない程度の店のことだ。
勘定方に給料の指示を出しているのは副長の仕事なので、沖田は土方がいくら貰っているのか正確には知らない。でも一番隊隊長は伊東などの例外を除けば副長に次ぐ役職だったし、討ち入りの多かったときなど危険手当で土方より貰っていた月もあるのではないかと思う。
「だってこんなことろ、高いでしょう」
姉への仕送りをしていた時はともかく、今は沖田だって持っているのだから先に言ってくれたら支払うつもりはあった。
「高いからこそ奢るんだよ、ばか」
男を立てろという口振りだった。でも沖田はこんなところで奢られてしまったら、それこそ逃げられないと感じてしまう。何から逃げるのかはわからないが、逃げるなら今しかないと警鐘を鳴らしている。
エレベーターの少し前で立ち止まってしまった沖田を土方は振り返った。
「心配しなくても個室だから、テーブルマナーとか気にしなくて大丈夫だ」
土方は何を勘違いしたのか、そんなことを言って沖田の腰を抱いた。そのままずるずると連れられるがままにエレベーターに乗り込んでしまった。「ごゆっくり」とお辞儀をしたまま顔を上げないボーイを置いてエレベーターのドアが閉まるのを、いよいよ退路を断たれた気持ちで眺めていた。
エレベーターから降りると案内係のボーイから内線が飛んでいたのか、名乗る暇すらなく土方が予約していた個室まで誘導されていく。
「お前何飲む?」
酒のリストを渡されて土方にそう尋ねられた。舌に馴染んだ鬼嫁など当然メニューにはないし、見てもよくわからない。水がビールより高値に設定されていて混乱した沖田は、潔く土方に全て任せた。丸投げしたとも言うが、そもそもこんな店だなんて聞いていなかったのだから仕方がない。上品な酒を小さな器に注がれて、慣れないなと思いながら飲んでいると料理が順番に運ばれてくる。沖田は嫌だ嫌だと思っていても、美味いものを口にすれば多少は緊張がほぐれていた。
「ん、これうめぇ」
「そりゃよかった」
美味いものを食べに行くと言ったのは土方だったのに、土方は味などわかっていないのだろう。ずっと眉間に皺を寄せて、機械的に料理を口に放り込んでいる。
「マヨネーズがねぇと物足りないですかィ?」
試しに沖田が尋ねたが「んなことねぇよ」とぎこちなく答えられただけだった。
その後特に会話が弾まないまま、最後の甘味と茶が提供されてしまった。土方とは長い付き合いで横にいても会話がないことなどザラにあったが、気まずい無言というのは沖田にとって初めてだった。
沖田が甘味の最後のひと口を口に運ぶのを見届けてから、土方はようやく本題に入った。
「お前さえ良ければ、明日からのヒートは避妊しないで抱きてぇと思ってる」
食事中に切り出さなかったわけだと沖田は察した。土方にとって決意のいることであり、沖田の出方によっては食事どころではなく店を後にすることになるだろう。
「意外でさァ……土方さんはてっきり子供なんて要らないって言うタイプかと」
とりあえずはなぜ、こんなことを急に言い出したのかを探りたくてそう聞いた。
「まあ二年前とかじゃ考えられなかったけどよ。最近はそれもありかなとか……俺のというよりお前の子が見てみてぇのが本音だな……」
ここで沖田はおや? と思った。土方が珍しくはっきりと言い切らず、しどろもどろ言い訳のようなことを重ねているのだ。よく見ると彼の目は泳いでいる。テーブルの上で組まれた両手は爪の跡が付きそうなほど食い込んで、カタカタと震えていた。緊張しているのだ、あの土方が。本気で言っていると察してしまって沖田は茶化して誤魔化すのを諦めた。
「……産むまでは俺がやるしかねぇですけど、そのあとは土方さんが育休取って頭抱えて生きてくだせぇよ」
「ああ、まあそのあたりは大所帯だしなんとかなるだろ。落ち着いてるとはいえお前がずっと不在なのも困るしな」
「土方さんの育休中に副長の座は俺が頂くんで心配しないでくだせェ」
「ブレねぇなぁ手前ぇは……」
「……そろそろ帰りやす?」
話が終わって、コーヒーも飲み終わったのでそう提案した。個室とはいえ専属の給仕係が控えてるこの部屋ではゆっくりくつろぐことすらできない。沖田の質問に土方は「あー」とか「うー」とか言いながらまたなにやら悩んでいる。
「……他にもまだ何か?」
「上のホテルに部屋が取ってある。ヒートの間過ごせるように今日から一週間分」
「……まじでか」
レストランを後にしてホテルへ移る際、今日から泊まるって言ってくれればよかったのにと沖田は言った。土方は下着など必要な物は全てまとめて持っているという。妙に荷物が多かった理由がやっと理解できた。最初から言ってくれれば自分で用意したのにとも思うが、その理由さえも沖田にはすぐ察せた。子供の話を断られたらそのまま泊まるのは気まずいから言い出せなかったのだろう。ヘタレなところがある土方らしいが、だったらこんな直前で切り出さなければいいのにとも思う。そろそろヒートが始まるというタイミングで、子供が欲しいと言われたオメガの気持ちはアルファである土方にはわからないだろうが。
あらかじめチェックインしてあったのかレストランから出てそのままホテルの部屋まで案内される。乗り込んだ高層階行きのエレベーターはガラス張りで夜景が綺麗に見えている。
「ターミナルがよくみえらァ」
町の象徴でもあるあの建造物は何回も破壊されて修復されてきた。夜だというのに今もたくさんの宇宙船が離発着しているようだ。
「そういえば土方さんは行ったことあるんですよねィ、宇宙」
「誰かさんのおかげでたくさん渡り歩いたな」
「へぇ」
沖田は聞いては見たものの、対して興味もなく適当に返事をした。ちょうどそのタイミングでエレベーターが目的階に止まって扉が開いた。
ルームキーを差し込むと、大きな窓からエレベーター同様夜景が出迎えてくれている。普段ヒートの際に泊まっているラブホは窓などないのでそれだけでも雰囲気が違う。思わず窓際まで歩み寄ってターミナルをみていると、荷物を置いてから土方も沖田の元へきた。
「今度行くか?」
「え?」
「俺も煙草追い求めてたら変なことになっちまっただけで、旅行って感じじゃなかったし」
別に行きたいと思ったわけじゃないとか、どこの星に行くのだとか、言いたいことは色々あった。でも一番気になってしまったのはひとつだった。
「土方さんと二人で……? なんかそれって――」
――新婚旅行みたいだなァ。
飲み込んだ言葉は土方に伝わってしまったようだ。
「合ってんだろう?」
今日は全くもってよくわからない日だと沖田は思う。普段あんなにわかっていた土方のことが全くわからない。沖田が戸惑っていると、土方はポケットから小さな布貼りの小箱を取り出した。
「これからガキ作ろうって言ってんだ、新婚旅行で合ってんだろ」
そう言って箱を開けると中には揃いの指輪が二つ入っている。そのうちの一つを取り出し、沖田の左手を取ってその左指へ指輪を通す。
なんで、なんで、どうして。番ではあったがこういった仲ではなかった認識だった。急激な展開についていけず沖田は目の前がグルグルしてしまう。でもそれを土方に悟られるのが悔しくて、結局憎まれ口だけがでてしまう。
「これ俺が断ったらどうするつもりだったんです?」
「そんときは屯所の引き出しにでも入れといた」
「本当中途半端ですよねィ土方さんは」
レストランを予約して、ホテルの部屋に、指輪まで用意しておいて。それでもなお断られたときの予防線を一個ずつ張っている。これでは自信があるのかないのかさっぱりわからない。
土方は残りの指輪を箱ごと寄越した。少しだけためらったあと、沖田は箱から指輪を取り出し土方の指へと通す。心の中にずしんと鉛玉が落ちてくるような、そんな気持ちになった。
一息ついてから沖田は改めて部屋の中を見渡した。たった二人で過ごす部屋なのに広くて豪華だ。
窓から見える絶景だけではない。質の良いベッドに、屯所の数倍の大きさのテレビ、部屋の中に用意されているミニバー、浴槽にも大きな窓が付いていて景色を楽しみながら風呂に入れるようになっている。
「アンタこれどんだけつぎ込んだんです?」
土方も沖田もそこそこ収入はある方ではあるが、江戸を追われている間無給だった期間もある。幸い隊を維持する金は別にあったが、隊費で落とせないような隊士たちの私用な物を幹部が奢ったりして出ていくものも多かった。そんな状況が続いていたというのにヒート期間丸々、セックスする時間を過ごすためにこんな場所を取るなんて思いもしなかった。
「ケジメが必要だったんだよ」
食事に、ホテルに、指輪に。つぎ込まれた金額が多すぎて目眩がしそうだった。それだけ本気なのだろう、土方は。
風呂に入ってソファに腰掛けながら適当にテレビをザッピングした。沖田と交代で入った土方も風呂から出て、沖田の隣に腰掛けた。何気なくそちらを向けば突然キスをされる。
「……しやす?」
沖田が問いかけると土方は優しく笑って頭を撫でた。
「明日からいっぱいするんだから今日はゆっくり休め」
もう一度キスをして、それから立ち上がってベッドに行ってしまった。テレビを消して沖田が追いかけると布団をめくって招き入れてくれた。
同じ布団で二人きり。喧嘩をしない、セックスもしない。でもキスはする。そんな夜は初めてだった。
早朝になると身体が熱くて、それで沖田は目を覚ました。起きた瞬間の状況が一瞬では飲み込めず、ぼんやりと考えてそうだったと思い出す。左手を宙にかざせば銀色のリングが朝日を弾いてキラキラと輝いている。
――そうだ、今日直接抱かれてしまう。
指輪を胸元で握りこむようにして考える。どうして自分だったのだろうと思うと込み上げるものがあって泣きたくなってしまった。でも身体の方は泣いている場合ではない。起き上がって部屋のミニバーの冷蔵庫からミネラルウォーターのボトルを拝借する。おそらく別料金だろうがここまで来たら誤差の金額に違いない。遠慮なく開封してまずは喉を潤した。冷えた水が上気した身体に染み渡る。それから次に昨日脱いで椅子の上に置いておいた着替えの中から錠剤を取り出して口に放り込んだ。オメガであれば誰でも持ち歩いているそれを、ミネラルウォーターで胃の中へ押し込んだ。
そうしている間も心臓はバクバクと大きな音を立てていてうるさい。本格的にヒートが始まっているようだ。いつもはもう少し緩やかに始まるのだが、番にプロポーズされたり隣で寝たりされた影響が出ているのかもしれない。仕方がないとため息をついて、冷蔵庫からもう一本ミネラルウォーターを取り出した。
「土方さん起きてくだせェ」
キンキンに冷えたミネラルウォーターのボトルを土方の頬に付けると、ヒェッっと声を出して彼は飛び起きた。
「つめて! なにすんだ総悟!!」
そう怒鳴った土方だったが、すぐに理解して甘い顔をした。ボトルを受け取って中味を飲んで、それから沖田の手を引いてベッドに引きずりこむ。
「スッゲェ匂い。こんな時間からそうなるの珍しいな」
「アンタがそうさせたんじゃないですか」
「興奮してんだ?」
今までずっとゴム越しに抱かれていたのが、今日初めて直接抱かれると宣言されたのだから意識しない方がおかしい。沖田の気持ちを置き去りにして、沖田のオメガとしての本能は歓喜を上げている。
「土方さん、早く……」
そう言って沖田は着ていた部屋着を自ら肌蹴させていく。そんな番をみて土方とて冷静ではいられない。
「総悟……!」
荒々しく唇を合わせて中に舌を入れる。ヒュッっと小さく丸まった沖田の小さな舌を解くようにして、代わりに自分のものと絡ませる。
「んっふっ、んん」
合わさった口と口の間から僅かに声が漏れる。歯茎を、上顎を次々と舌先で愛撫してから、ようやく口を離して解放した。はぁはぁと息を整えている沖田の胸は上下に大きく揺れている。その胸元にある二つの飾りへ今度はターゲットを移す。
片方を口に含んで舌で転がし、もう片方を指先でコリコリと刺激してやる。
「あっあっ、気持ち……」
ぷくりと存在感を増していく胸の突起と共に、沖田の嬌声も大きくなっていった。
胸だけだと満足できなくなってきたのか、沖田はスリスリと足を擦り合わせている。胸元を舐めながら片手で足を割って奥の蕾を指で突いた。
「んんっ……!」
閉じていた蕾はちょっとの刺激であっという間に開花する。
「ふっ、あっ、やあっ!」
沖田は口ではやだやだと言って頭を横に振っているが、自分で大きく足を広げて刺激を求めている。
前回のヒートをテレフォンセックスで済ませてしまったため、土方が触るのは半年ぶりだった。指を一本差し込むと待ち侘びていたようにズブズブとそれを飲み込んでしまう。
「んっんんっ、ふっ、あ」
あまりにも簡単に入ってしまったのでそのまま指を増やして二本目を挿入した。耐えきれなくなってきたのか沖田が土方の首に腕を回した。途端に動きにくくなったがやめさせたくはないため乳首を吸うのを諦め、再び口を吸った。指を動かすのはそれでもやめない。久しぶりとはいえ土方のモノを受け入れることに慣れた筒はジュボジュボと音を立てて指を三本取り込んだ。
沖田以上に沖田の身体を把握している土方は、的確に善いところを刺激して沖田はすっかり溶け切ってしまっている。
「総悟……挿れるぞ」
そう言って沖田の右足を担ぎ上げて土方のナニが、膜を挟まないで直接沖田の後孔へ触れてくる。そこは萎縮するように、しかし期待するようにそこはキュッと震えていた。
「……ヘィ」
沖田の返事を受けて土方はゆっくりと腰を進める。
「んっ! あっあっあっああ――!」
沖田の中は欲しかったものを与えられて、なんの抵抗もなく奥へ奥へと招き入れていく。
「全部入った……」
土方の独り言に近いセリフを聞いて沖田は視線を落とした。沖田の下生えは薄いため自身の股間と土方の股間がピタリとくっついて、土方の性器が丸々埋め込まれてしまったのがハッキリと見える。
「んっ……だめ、っん!」
まだ馴染んでいないうちから土方は腰を打ちつけ始めた。
「あっふやぁあっあっ、ひっ土方さん、あっはぁ……!」
ヌチャヌチャと泡立つ音がする。その一方でコンドームがないためひっかかりもなく肉棒を直接受け止めて、パンっといつもより大きな音で肉と肉がぶつかる音がする。
「ヤベェ、すげぇ気持ちいい……」
土方がそう呟いた。沖田は挿れたことがないのでわからないがコンドームの有無でやはり違うようだ。
「総悟、総悟、総悟!」
何回も何回も名前を呼んでゆさゆさと身体を揺さぶられる。
「……土方さ、ん、土方さん……」
釣られるように沖田もまた名前を呼んだ。
「熱いな、お前のナカ。知らなかった」
「……気持ちいいですかィ?」
「すげぇイイ」
即答だった。それを聞いて沖田は少し笑った。
「それはよかったですねィ」
「……なんで他人事? お前は善くないのかよ」
「イイですよ。でもそれはいつものことなんで」
「チッ」
こういうときに突然デレるのは相変わらずだ。普段が普段なだけに土方は簡単にギャップにやられてしまう。
「じゃあ今日はもっと善くしてやるよ」
「ひぇ……俺は、土方さんがよければそれでいいでさァ」
「遠慮すんなよ」
土方は完全に瞳孔が開いて悪役のような顔をしていた。激しく動くだけでなく、前立腺がピンポイントで土方の欲望にゴリゴリと押し潰されている。
「んあ……あっあっはぁ……ん! 土方さんんっ……ひっっやぁだめ、あっあっ!」
ヤダヤダと叫ぶが土方は止めない。ピストンに合わせてどちらのものかもわからない愛液が泡立って弾ける。
「気持ち、気持ちいい……死んじゃう、無理! 無理って言ってんでさァ土方このやろー!!」
普段痛みに強く、どんな怪我を負っても泣き言を言わない沖田が強すぎる快楽を前に限界を口にする。そして沖田の身体はそれに合わせてアルファの子種を絞り取ろうと強く痙攣した。
「きっつ……」
かなりキツく締め付けられてはいるが、それを上回る愛液のおかげで動きは止まらない。ヌルヌルと動かしていると絡みつく粘膜が直接感じられて気持ちがいい。
「総悟出すぞ」
「土方さん、奥、奥にくだせェ!」
悲鳴のような懇願を受けて土方はついに子種を沖田の体内へと注ぎ込んだ。
「ああ――っ!」
ドクンドクンと脈打つように吐き出されたのを感じて、沖田は恍惚とした表情を浮かべて自身もイった。
二人はしばらく動くことができず折り重なるようにしてベッドに倒れ込んでいた。どれくらいそうしていたのだろうか。土方がようやく起き上がって沖田の体内から自身を引き抜いた。封をされていたものが外されたことによって、収まりきらなかった白濁色の液体が孔からドロっと流れ出しているのがひどく扇情的で視覚にくる。
「土方さん……若すぎだろィ」
たった今吐き出したばかりだと言うのにもう立ち上がってしまったことが沖田にしっかりバレている。
「中出しなんて初めてしたから仕方がねェだろ!」
「ダメとは言ってやせんよ。その代わりもっとくだせェ」
そう言って沖田は硬くなった土方のナニにそっと触れる。
「ん……」
それを合図に二人はまた行為に没頭していくことになる。
お互いもう何度果てたのか数えるのもやめた時、何回もお腹に注ぎ込まれては溢れ出した精液を土方が拭いながらポツリとつぶやいた。
「後悔、してるか?」
それをこのタイミングで聞くのかと沖田はビックリした。彼はしばらく考えこんでから、質問には直接答えずに呟いた。
「……俺がアンタにあげられるものって少ないですねィ」
一番の愛は姉に、誰にも負けない剣の腕は近藤に捧げてしまった。沖田にはもう身体ひとつしか残っていない。そんなことを言う沖田に土方は悲しくなる。
「そんなことねェだろうが……そんなことねぇんだよ」
妖刀に憑かれたときも、真選組を離れて一人で岡っ引きをやっていたときも。沖田はただ一人土方が来るのを信じて待っていた。そんな人間は他にはいなかったのに。
真っ直ぐな信頼をくれる沖田を手放したくない。お前が貰えればそれだけでいいのだと。土方はこの時それを伝えるべきだったのだ。しかし長年連れ添ったがゆえに、素直にそれを口にすることはできなかった。少しだけ掛け違えたボタンは直されることができず、次もどんどんと間違えたまま掛けられていく。
◇
ヒート後に仕事に復帰した沖田は指輪を指にははめず、チェーンに通して首から下げていた。それを見た土方は慌てて呼び止めて確認した。
「総悟、その……もしかして首輪の方がよかったのか?」
ドS王子である沖田に首輪というのがどうにもしっくりこずに指輪にしたのだが、一般的に番には首輪を送ると聞く。指輪をわざわざ首に付けているということは、自分が知らないだけでオメガにとって首輪の方が落ち着くのだろうか。土方が焦って確認したというのに、沖田はそれを見てニタリと笑った。
「意外と女々しいんですねィ土方さん。指になんか付いてんの違和感あって慣れねぇだけでさァ。アンタがどうしてもって言うなら、非番のときには付けてやってもいいですぜィ」
カラカラと笑う沖田に土方は深い息を吐いた。
「なんだよビックリさせやがって」
そう言った土方の左手には銀色の輪っかが輝いている。それを見て沖田が問いかける。
「……土方さんは気にならねぇんです? こう刀抜くときとか鞘に当たるじゃねぇですか」
「ん? 俺は気にならねぇな。オメェの方が指細せぇし、それで気になるのかもな」
女性向けの華奢なデザインは仕事柄耐久性が乏しそうでやめた。しかしそこまでいかずとも、もう少し細身のデザインにすればよかったと土方は心の中で反省をした。指輪のサプライズが一般的にあまり喜ばれないことは知っていたのだが、指輪でも用意して自分にとって後に引けない状況を作らないと関係を進めることについて言い出せそうになかったのだ。
「まあ嫌じゃないならよかったよ。……それより総悟、体調の方はどうだ?」
「え……昨日まで尻にナニ突っ込まれて『総悟、お前の中気持ちいい……中に出すぞ……』とか言われてたんで寝不足ですけど、もしかして寝てきていいんですかィ?」
「そうじゃねぇよ! 妊娠の経過だよ!! 隊務の調整とかもあるから早めに知りてぇんだわ」
「土方さんせっかちですねィ。流石にまだわかりやせんよ。あと一週間くらいしたら病院行ってきやす」
「……おう」
土方は待ちきれないのかソワソワしながら頷いた。
その一週間後、病院から戻った沖田は妊娠してなかったことを告げる。
「え、できてなかったのか?」
ヒート中にアルファと避妊なしでセックスしたオメガはほぼ妊娠すると言われていたので土方はかなり拍子抜けした。
「そうですねィ。……子供は授かりもんって言うでしょう。俺ァ特に不規則な生活してるんでなおさらそういうこともありまさァ」
確かに夜勤もあれば、大きな事件があれば徹夜だってある。攘夷活動が活発だった頃と比べれば大した頻度ではないが、それでも沖田の活動量は一般的なオメガの範疇ではない。
土方もその説明に納得したし、できてないのであれば仕方がない。話は一旦そこでおしまいになった。
それから半年が経ったが沖田は妊娠しなかった。しかしそれだけでは済まず、ヒートの後体調を崩すようになっていた。業務に支障をきたさないレベルとはいえ、それは誰から見ても明らかな具合の悪さだった。
「総悟、テメェ顔色ヤベェぞ」
こう言ったことに口を出すと逆効果だとわかってはいても、土方がついそう口にせざるを得ないほどの酷さだった。病気か、そうでないというのであれば妊娠してるのではと思いたくなるような顔色の悪さだ。避妊しないで三回のヒートを過ごしたが今のところ沖田は妊娠した様子はない。発情期にセックスすれば、ほぼ確実に子供ができるものだと思っていた土方は二回目以降は少し疑った。しかしその後毎回ヒートが来ているので妊娠していないのは確かなようだ。
「元々ヒートの後は調子悪かったのが、最近ひどいんでさァ。俺も歳ですかねィ」
他人事のように沖田が言ったのを聞いて、お前がそうなら俺はどうなるんだよと少しだけ思う。
「まだそんな年齢じゃねぇだろ」
でも一週間弱セックスし続けるのは土方にとっても負担があることではある。だからそんなものなのかと深くは考えなかった。オメガはアルファより数が少なく、土方は沖田以外のオメガを知らない。沖田が言えば、それが真実なのだと思い込んでしまっていた。結果からいえばこの時もう少し問い詰めるべきだったのだろう。もしくはヒート中のセックスにも関わらず沖田が妊娠しなかった理由を、もう少し疑問に思うべきだったのだろう。土方は結局そのどちらもしなかった。
そしてこの数日後にかかってきた電話で、それを後悔することになるのだ。
それは土方が副長室にて書類仕事をしていたときのことだった。画面に表示されたのは沖田の名前だ。組に居れば連絡を取り合うことはよくあることで、特に隊長格である沖田とは公私共に電話をかけ合う。今日は沖田は遅番で午前中は散歩に出ると言っていた。道中で不貞の輩でもしょっ引いて連絡してきたケースなどがすぐに思い浮かぶ。そのため深く考えずに携帯を耳に当てた。しかし「土方くん?」と予想外の声が聞こえてきて思わず息をのんだ。
「……万事屋か?」
会えばふざけたことをしあったり喧嘩もする人物ではあるが、誰よりも真っ直ぐとした芯を持った侍だ。間違っても沖田の携帯を使って嫌がらせをしてくるような相手ではない。沖田と共謀しているのであれば話は別だが、それにしたってわざわざ電話を使ってくるほど嫌がらせしてくる理由もなかった。となると電話の持ち主が携帯電話を落としたか、自分では電話をかけられない状況であることが窺える。
バクバクと跳ねる心臓の音を聞かないようにして、電話の相手である坂田の言葉を待った。
「落ち着いて聞いて欲しいんだけど、沖田くんが倒れた」
いつだって土方の嫌な予感というのは当たるものなのだ。
◇
坂田から沖田の搬送された病院を聞いて慌てて駆けつけた先で、医者から告げられたのは土方が想像もしていなかった現実だった。頭が真っ白になりながらも沖田にあてがわれた病室へと向かった。ドアを開けてみると個室で一人、沖田が寝ている。点滴が繋がっている腕はひどく細い。沖田は元々の体質で必要最低限の筋肉しかつかないとぼやいていたが、それにしても以前より確実に肉が削げ落ちている。
「そうご……」
静かな病室に土方の声だけが反響した。沖田は土方の来室には反応せず、ベッドに横になったまま動かない。土方がそっと沖田の手を握る。それでも沖田はまだ起きなかった。
こんなことになるまで相談ひとつなかった。そのことに絶望を感じる。仲間なのに、上司なのに、番なのに。そして恋人になれたと思ったのに。気がつかなかった自分にも嫌気がさす。いつだってそうだ。土方は何度も沖田に騙され、大事なことは全て終わってから知らされる。卵巣の摘出手術だけは事前に知ることができたが、それは彼の姉が教えてくれたからに他ならない。
「総悟、今俺、監禁されたときよりキツイんだけど……いや、あんときもヤバかったけどよ」
倒れた沖田を抱え込んだことが土方には何度かある。沖田によって監禁されたときもそのうちの一つだ。その度に、こんな仕事をしていながらも彼を喪う覚悟ができていないことを思い知る。
ふと視線を上げるとベッド脇に置かれたテレビの前に土方が贈った指輪が、チェーンに通った状態で置かれている。入院時の検査のために外されて、そのあとここへ置かれたのだろう。何気なくそれを手に取り沖田の指へはめた。贈ったときはピッタリだったはずの指輪は今は緩く、ちょっとした動きで抜け落ちてしまいそうな状態だった。それを見て土方は背筋が凍り付いた。顔を見てやつれているのは気がついていたが、ここまでとは思っていなかったのだ。
どれくらい手を握って祈るような時間を過ごしたのか。土方の体感では数時間のように感じるほどの長時間だったやっと握っていた手の指先がピクリと動いたあと、沖田はゆっくり目を開けた。その瞬間、土方は泣きたいほど感謝した。生きているなら話ができる。きっとやり直せると。
「土方さん……」
沖田は二、三回瞬きをした後、状況を飲み込んだようで困ったように目を泳がせた。これは彼が悪戯に失敗したときの癖だと土方は知っている。
「倒れた理由はわかってるな? 緊急避妊薬の常用と、強い心労だそうだ」
沖田は開けたばかりの目をつぶって、ふうっと大きく息を吐いた。
――緊急避妊薬はあくまで緊急用のものなんですよ。子供がいらないなら番のためにもしっかりと避妊してください。
沖田の番だと告げて病状を医者に問いただしたところ、そう説教されてしまった。鬼の副長にここまで強く言える相手は万事屋以外にもいたなんてと、居合わせた山崎が診察室を出た後ぼやいていた。
中に出すと決めたときに、意志の疎通ができてるものだと思い込んでいた。子供ができてもいいものだと。しかしそう思っていたのは土方だけで、沖田は違った。副作用の強い緊急用避妊薬を常用してまで、妊娠しないようにしていたのだ。嫌なことは嫌だと、気に入らないことは気に入らないと言うのが土方の知っていた沖田だ。だからまさか、という気持ちがまだ心の中にどっかりと居座っている。
「なんで黙ってそんなことをした……何がそんなにお前を追い詰めちまったんだ……何が嫌だったんだよ」
「嫌だったんじゃないんでさァ。嫌じゃないからダメだったんです。土方さんから言われたことが嬉しくて、だから嫌だとは言えやせん」
だって、と言っているうちに沖田はポロポロと涙をこぼした。
「土方さんと番になって……抑制剤要らないのは楽だし。セックスも気持ちいいし。でもずっと言い訳してやした。本能だから仕方がないって。だから許して欲しいって」
「……許すって、誰にだ」
沖田はたった四文字「姉上」とつぶやいた。それだけだったが土方には意味がわかる。通じたからこそショックで頭が真っ白になった。この目の前の男は、この期に及んでまだそんなことを考えていたのかと。自分も沖田も確かに、好きだとかそう言った気持ちを伝えることなく行為に及んだ。言わなくても伝わっているものだと沖田の気持ちの上に胡座をかいていたのだ。
土方は沖田の手をぎゅっともう一度強く握った。それからゆっくりと、はっきりと伝えていく。
「手前を番にしたのは俺だ。俺が選んで決めた。だからお前が気に病むことなんなねぇんだ。ガキが好きなの知ってたからお前もてっきり欲しいかと思ってたけど、いらねぇならそれでもいい」
沖田は頷かなかった。土方の本心が他にもあることを悟っているのかも知れない。しばらく無言が続いたあと、全部白状すると土方は言った。
「手前の姉貴に明日も知れねぇ俺とじゃなくて、他の男と幸せになって欲しいと思ったのは本当だ。……でもそれだけじゃなくて、オメェの剣に惚れてるんだ、俺は。近藤さんのために、真選組のために……俺のために、オメェの剣は絶対必要だった」
沖田は土方の言葉を黙って聞いている。痛みを堪えるかのように悲痛な表情を浮かべながらも、真っ直ぐに土方を見ていた。
「……だが弱みが近くにいるとわかればオメェもアイツもどうなるかわからねェ。総悟の剣が万が一にでも鈍くなることがあっちゃならねェ。だからアイツには江戸に来て欲しくなかった。……邪魔だったんだよ」
土方はあえて強い言葉を使った。誤解を恐れないのではなく、誤解されてもいいと思ったからだ。土方はもちろんミツバのことだって大切だった。しかし死んでしまった者に対して気を遣って、今この瞬間目の前の生きている沖田を失うことだけは避けたかったから。巡り巡ってそれは、弟が大好きだったミツバのためにもなるはずだ。
「恋愛の意味でも大切だと気がついたのは最近だが、でもそのずっと前から俺の中ではお前が最優先なんだよ、総悟」
やっと決まったミツバの縁談。先の長くはない命。それでも天海屋を捕えることを待たなかったのは、沖田が真選組から追われないためだった。ミツバが正式に籍を入れる前に、そして世間に露呈する前に片付ける必要があった。沖田は土方が自分のためにそうしたと勘違いしているがそれは違った。土方は自分自身のため、ひいては真選組のためにそれを選んだ。ミツバの気持ちも、沖田の願いもわかった上で、自分のためだけに動いたのだ。沖田が真選組の、自分の近くにいることがとにかく最優先だった。
沖田は俯いてしまって表情が見えない。見えないまま強く抱き寄せる。
「お前のことが好きだよ、総悟。元気なお前が抱けるなら、ゴムなんかあってもなくてもどっちだっていいんだ。子供の件もいったん白紙にしよう」
必要だったのはムードのあるレストランでも指輪でもなく話し合いだった。
土方の胸元でグスっと啜り泣く音が聞こえ、しばらくして沖田は口を開いた。
「俺……一生言うつもりなかったんですけど、土方さんが好きでさァ」
沖田は土方の胸元から離れて、自身の指にハマっている指輪をみた。
「これ貰ったのも嬉しかったんです。でも姉上のこと考えたら喜べなくなっちゃって」
指につけることができず、かと言って捨て置くこともできずに首から下げておくことにした。
「今度からそういうときは俺に言え。俺も背負うから。そのために一緒にいるんだ。無理なら喜ばなくてもいいし、俺も今後は勝手になんか買ったりするの止めるよ」
「……へぃ」
二人は顔を見合わせて、それからゆっくり触れるだけのキスをした。
「ねぇ土方さん……思ったこと言ったら、本当になんでも受け止めてくれるんです?」
「ああ、……まあできる範囲でな」
かっこよく断言したいところではあったが今すぐ死ねとか副長の座をよこせとか言われそうで、土方は結局予防線を張ってしまった。沖田はニヤリと笑って言った。
「土方さん、俺のこと抱いてくだせぇ。今、ここで」
「はっ!? それはどっちの意味だ?」
「もちろんアレの方でさァ」
張っておいた予防線を出そうかとも思ったが、沖田はふざけている様子ではない。
「病室だぞ」
「でも今したいでさ」
「……ゴムも持ってねぇ」
「もう必要ねぇです。まあ今発情期じゃねェから子供もできないだろうし、無理したから今後もできないかもしれやせんけど」
土方は押し黙って考えた後、わかったと答えた。それから入口の方へ向かって呼びかけた。
「いるんだろ山崎!」
「……はいよ」
病室のドアを開けて山崎は渋々顔を覗かせた。
「聞いてたか? 耳塞いで見張ってろ」
「……沖田隊長倒れたばかりなんですから、無理させんでくださいよ」
山崎はそう言って再びドアを閉めた。土方は念のためベッドの周りをとり囲むカーテンも閉めた。個室のため今まで開けられたままだったが、こうしておけば万が一ドアを開けられてもすぐに見られることはない。体裁的な意味もあったが、沖田の感じてる姿を誰にも見せたくなかった意味合いも強い。
待ちきれなかったのかカーテンを閉めるなりすぐに土方の手を引いてベッドの上へと引き入れた。
「おい待て、靴! 靴脱ぐから!!」
「チッ」
沖田は乱暴に土方の靴を自分の足を使って脱がせ、ベッドの上から投げ落とす。そしてそのまま土方の隊服のズボンにまで手をかけた。しかし腕についた点滴が邪魔をしたので一瞬躊躇したのち沖田はそれを引き抜いてしまった。
「ちょっ……いつになく積極的じゃねぇ? 発情期か?」
デリカシーのない土方の発言に沖田はムッとして答えた。
「……ヒートじゃねェのは土方さんが一番よくわかってるでしょう」
確かにヒート特有の甘い香りは感じられない。でもそれならばなぜ、ヒートのときより沖田がムラムラしているのか説明が付かない。
いくらなんでも点滴を抜いてしまうなど正気の沙汰ではない。倒れたとはいえ容体が落ち着いていたためモニタ類が付けられていなかったことを幸ととるか不幸ととるか。少なくともこの件で看護士が気付いて駆けつけることはないだろう。点滴のパックに残っている液体は多く、交換までの猶予はありそうだった。
そんなことを考えていると沖田はすっかり土方のズボンをくつろげ、股に顔を近づけていた。
「いただきます」
ペロッと舌で唇を舐めてから、沖田は土方の陰茎にしゃぶりついた。
「っう……」
沖田に裏筋を舐められるとそれだけでムクムクと陰茎は立ち上がっていく。大きくなったそれを満足気に眺め、それから先端をチュっと音を立てて吸った。何回か吸い付いたあとは舌で尿道をつついたり、カリの部分を甘噛みしたりする。
たっぷり時間をかけて土方の陰茎を唾液まみれにしたあと、見せつけるように土方の顔を見ながらゆっくりゆっくりと全体を飲み込んでいく。
「総悟……!」
小さな口内にズッポリと収められるとそれだけで最高潮に興奮してしまい、土方は沖田の頭をつかんで腰を動かす。
「んん、ぐっ……」
喉を突かれて沖田が苦しそうな声を上げるが止められない。土方が出したい、と思った瞬間それが沖田に伝わったのだろう。彼は急に本気で抵抗して土方を制した。
「ダメです土方さん、イくのはこっちでさァ」
病院着のズボンと下着を脱いで、沖田は座った状態の土方の上にまたがって首に腕をかけた。そして限界まで張り詰めている土方のナニに、自分の孔を擦り付けてくる。陰茎を舐めながら興奮していたようで、そこはグチュグチュと濡れて音を立てている。
「ほんと今日はどうしたんだよ……」
ヒートの最中でも受け身な沖田がここまでしたことはない。
「だって土方さんがいけないんでさ。あぁっ……!」
沖田が浮かせていた腰を落として、孔にあてがっていた楔を挿入していった。お互い座った状態でつながってしまった。
「おい、いきなり挿れんなよ!」
まさか本当に急に入れるとは思っていなかった土方は慌てたが、沖田はそのまま上下に動きをつけて気持ちがいい箇所を探っていた。
「ふっ……あっあっ、ここ」
「……ここか」
「あ――っ!! 気持ちい」
下から腰を突き上げると沖田は腰を大きく反らせて喘いだ。その声の大きさに慌ててしまうのは土方だ。
「ここ病院なんだ、静かにしろよ」
「あっあっ」
ネジが飛んでしまっているのか土方の言葉は沖田に届かない。仕方がないため土方は沖田の頭を手で引き寄せてキスをする。
「んんん、うっん……」
嬌声が曇った音へ変わり、そのまま二人で何回も上下に跳ねる。
興奮しすぎて息継ぎがうまくできず口を離せば沖田は再び声をあげる。
「あっあっ、好き……土方さん、好き、好き」
今まで言えなかった分を取り返すかのように彼はそればかりを口にしていた。
「総悟、もう出る」
「ん……出してくだせェ」
あらかじめ口で射精寸前まで高められていた土方はあっけなく沖田の後孔で果ててしまった。
沖田は満足したのだろうかと見ると、土方の吐き出した精液をティッシュで拭いながらも珍しく機嫌が良さそうだった。
「へへっ、ヒートじゃねェときのえっち初めてしやした」
あまりにも嬉しそうにしている沖田を見て、最初はかわいいところもあるものだと見ていた土方だったがハタっと気がついて青ざめた。土方はもう若くはないし、ヒートで一週間ガッツリとセックスをするのでそこまでムラムラすることもなかった。屯所はいつ誰が飛び込んでくるかわかったものではないし、わざわざラブホに行くほど必要にも迫られておらず結果としてヒートの時だけしていたというわけだ。
「……もしかしなくてもお前、俺がヒートにあてられたから今まで抱いてたと思ってたか?」
「まあ。あとうなじ噛んじゃったから責任感じてるのかなとか?」
とんだ誤解である。その状態で子供が欲しいとか言い出せばそれは確かに拗れるなと納得できる状態であった。
「責任はもちろん取るつもりだったが、そもそも九つも下のお前を抱くのに気持ちがないわけねェんだよ」
ずっと大切で、途中から好きだと思い知って、ヒートを起こした沖田を見て運命だと気がついた。確かにキッカケはヒートだったが、逃したくなくてうなじに噛み付いたのだ。
「順番が逆なんだよ。うなじを噛んだから責任を取ってるんじゃねぇ、添い遂げたくて勝手に噛んだんだよ」
「……さっきのでわかりやしたよ。だから抱いて欲しかったんでさァ」
急に沖田が盛ったと土方は思っていたが、気持ちが通じたのが嬉しかっただけのことだった。
「……ところで総悟」
「言わないでくだせェ、俺も困ってるんでさァ」
話の間も沖田は必死でシーツについた精液を拭き取っていたが、乾くまでは時間がかかりそうだった。そもそも匂いが誤魔化せそうにない。
沖田が引き抜いた点滴はコードが虚しくぶら下がっているし、遠くからカラカラと回診車がこちらに近付いてくる音がする。併せて廊下の山崎が慌てたようにドアをノックしていた。
「……とりあえず窓開けるぞ」
「ヘィ」
土方は身なりを整えてから窓を開けた。この後のことを考えるとついそのまま窓から飛び降りて逃げてしまいたかったが、患者の飛び降り防止のため窓は少ししか開けられない構造になっていた。
「シーツは布団かぶせとけ。点滴はお前が寝ぼけて外したことにすんぞ」
雑な作戦を沖田に告げて、看護士の到着を待った。
沖田は三日間入院して退院することになった。退院日を無理やり非番にして土方は迎えに行った。くれぐれも気をつけるようにと医者に念押しされてでた病院の外は清々しい青空が広がっていた。
「総悟、今日はデートして帰るぞ。映画でいいか?」
「はっ!?」
沖田の入院中に土方はたっぷりと考えて反省した。デートも気が付いたうちのひとつだ。食事に行ったり、屯所で一緒のドラマを観たりすることはあっても、改まってデートというのはしたことがなかった。公私共にずっと一緒にいるからといえど、あんまりだと思った。最初から一歩ずつやり直していこう。時間ならこの先もまだいっぱいあるのだから。
土方の気持ちが伝わったのか沖田はニコリと微笑んだ。かわいいなと思ったのは一瞬のこと。
「映画ならアレがいいでさァ、最近始まった赤い着物の女VS白い着物の男」
「うるせぇ観るのはとなりのペドロ2だよ! 怖いわけじゃなくてそっちが見たいだけだからな! 全然怖くないけどな!!」
結局沖田によって土方はペースを乱されてしまうのであった。
「仕方がないから間を取って遊園地行きやしょうよ」
「なんの間取ったら遊園地になんの!?」
「ファミリー向けからホラーまで取り揃ってやすぜィ。あとほら、映画でも遊園地でもチューするのに変わりないじゃないですか」
「お前はホラー映画の最中にキスすんのかよ! 集中しろよ! 映画に!」
まったくもって意味がわからない。でもそんなやりとりすら、退院した今であれば尊いやりとりに思えてくるから不思議だ。
「今日は荷物もあるしお前も本調子じゃねぇんだ。遊園地は来月な」
土方がそう言ったら、沖田は頷いて土方の腕に抱きついた。
「……えっ」
「デートだから特別サービスでさァ。ねぇ土方さん、昼飯は焼肉がいいです。牛丸」
「……思ったより安上がりだな」
沖田があげたのは大衆向け焼肉チェーン店の名前だ。いくらでも奢るつもりでいた土方は若干拍子抜けした。
「今日はジャンキーなものが食べたいんです。わかりやせん?」
「……わかる」
土方も何回か怪我で入院したことがあるのでよくわかる。三食味の薄い病院の食事を繰り返しているとそういう気分になるのだ。
「じゃあ今日行くところは決まりだな」
そう言って二人は病院を後にした。沖田の左手には指輪がハマっていて、多分きっとすれ違うことはもうしない。