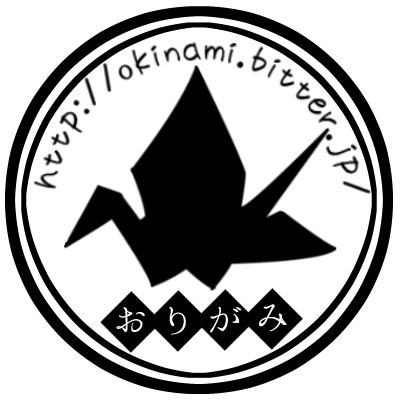
巡り合わせの愛2
――俺は万事屋を捜しにいくよ。
土方はそう言って江戸を去って行った。近藤はゴリラとの結婚に備えて花嫁修行へ行き、残された沖田が元真選組を取りまとめて桂の反対勢力をまとめることになった。
いつでも一緒だった真選組がバラバラに暮らし始め、しばらくしてから沖田は最初のヒートを迎えた。土方と番になる前は万が一を考えてちゃんとした施設に身を寄せていたが、番ができた以上他人を誘惑することはないため今回は一人で宿にこもることにした。番になってから二年はヒートのたびに土方が付き合ってくれていたため、誰もいない環境に戸惑いもある。なにより番ができるまでと、番ができた後では身体の構造から変わってしまっているのだ。沖田のナニは触れば気持ちの良い性感帯ではあるが、最近ではほとんど射精できなくなっている。一説では自分自身の精子で妊娠することを防ぐためとも言われている。
ヒートにおける自慰のハードルは、正直言って出して終わりにできていた番がいない時の方が低かった。しかし身体が番がいる状態であること、番が解消されていないということは土方はこの地球のどこかで生きているということでもあった。離れてしまった番との繋がりを感じることができるのは、肉体的には辛くとも精神的には満たされている。
気は進まなくとも沖田が湧き上がる熱を渋々処理していると、枕元に置いていた携帯電話が鳴った。休暇中とはいえ沖田は今現在組織のトップであり、指示が必要なこともあるため出ないわけにもいかない。しかし開いた画面に表示されていたのは想像していた相手、原田ではなかった。携帯を耳に当てると画面に表示されていた名前通りの声が聞こえてくる。
「総悟」
その呼び方で名前を呼ぶのは、この世にもあの世にも限られた人物しかいない。着信は沖田の番である土方からだった。
「そっち戻れなくて悪い……俺と番になってから一人でヒートは初めてだろ。大丈夫か?」
鬼の副長とは思えない過保護だ。江戸を離れる際に元真選組の隊長格に土方自ら、沖田のことを頼み込んでいたのにこうして電話までしてくるなんて。
しかしそれは杞憂ではなく、現に一人で達せずにいたところだ。でもそれを彼に教えられるほど沖田は素直ではない。
「芋掘りで忙しいんじゃあ仕方がないでさァ」
「ちげぇよ、こっちもゴタついてるだよ!」
殊勝だった口調が一瞬でいつもの怒鳴り声に変わった。それが沖田にとって何より嬉しく、つい鼻先で笑った。それを聞いて土方はふーっと大きくため息をついた。
「……案外余裕ありそうだな」
「へぃ、俺もどうなることかと思ってやしたが、終兄さんが意外と気が利いてて……」
「はっ? 終? オメェあいつに触らせてんのか?」
話の途中で土方が思わぬところで食いついてくる。天下の色男に余裕などない。剣の腕は信用してくれてるのに、色恋での信用はあまりないんだなと思うと沖田は若干面白くない。
「ちがいやすよ。ヒートだって言ったら色々持ってきてくれたんでさァ。飯だけじゃなくて道具も色々……あらら、土方さん大丈夫ですかィ?」
ガタンガタンとおそらく携帯電話を落とした音がした。動揺している土方を思い浮かべて、沖田は少しだけ気をよくする。
「お前なぁ……道具ってなにがあるんだよ」
随分と踏み込んでくる。恥ずかしがる間柄でもないので沖田は一つずつ説明していく。
「ローションにコンドーム、張型が三種類。なんとカラクリ式のもありやすぜィ」
土方はふうんと返事をした。口振りからして何か考え込んでいる印象だ。
「あとは?」
「そうですねィ、あとはオナホとか今の俺には使えなさそうなものがありやすぜ。……前はもっと気の利いたもん持ってきてくれそうな人がいた気がするんですが、それでも助かってまさァ」
「……そういや確かに他に適任が居た気もするけど誰だったかな……」
土方の隣でいつも使いっ走りをしてくれ、それでいて気が利いて秘密が守れる貴重な人物が。しかし今土方の隣には、モブにしておくにはキャラの濃いモブしかいない。
鉄ではないし、ならば誰だったかと思い出そうとしていると沖田が口を開いた。
「……前にも思ったことあるんですけど、ヒートんときに耳元で土方さんの声聞くのほんとキます」
言葉通り沖田の声には、抑え切れない色が滲み出ている。
心配した近藤だったり、元真選組の面々が必要なものがないかと電話で連絡くれたりもしたがそんなことはなかった。土方の声にだけ強く反応してしまう。
ただでさえヒートで頭が回らないというのに、土方の声を聞くと身体の奥が疼いて仕方がない。だから電話をはやく切り上げたかった沖田だったが、土方から恐ろしい提案をされてしまう。
「……じゃあそのまましろよ。付き合うから」
「はっ!?」
どういう意味かと困惑した沖田に、土方は悪魔のような提案を続けた。
「俺もするから、電話繋いだまましろよ」
「……土方さん、変態みたいですぜ」
「男はみんな変態だろ」
そんな馬鹿な話があるかと否定したかったが、沖田の周りには確かに変態か変人しか居ないので咄嗟に否定することもできなかった。無言を肯定と捉えたのか土方は話を進め出す。
「まず今何してたんだ?」
「ナニって……アレですよ」
完全に嫌だと言うタイミングを見誤った沖田が、ぼかして答えると「ちゃんと言わないと分からない」と指摘が入った。
「……ナニをアレしてたんでさァ」
それに対してふうんと土方は返事をした。電話で顔は見えないが絶対にニヤニヤした表情をしているのは沖田にもわかった。
「死ね! 土方コノヤロー!」
馬鹿正直に答えたのが恥ずかしくなった沖田がそう喚いて電話を切りそうになったが、土方はまてまてと慌てて静止した。
「いきなりナニを触るんじゃなくて、まずは乳首触ってみろ」
「えぇ……めんどくせぇです」
「ヨくしてやるから言うこと聞け」
確かに今までのセックスにおいて、土方のリードで気持ち良くなれなかったことはない。発情して持て余す熱を持っている沖田はこれ以上抵抗することはできなかった。
「ッ……んっふっ」
いつも土方がするように胸元を弾いたり転がしたりすると確かに興奮してくる。それは電話でも伝わっているようで土方も「たまにはいいなこういうのも」とか言ってゴソゴソと自分の準備を始めているようだった。
沖田が胸の飾りをいじって五分ほどしてようやく土方は次の指示を出した。
「そしたら下触ってみろ、もうドロドロしてるだろ?」
「……土方さん、実は隣の部屋とかにいやすか?」
あまりにも電話先にバレているので沖田は思わず襖の隣を見てしまった。
「ばぁか、何回抱いたと思ってんだ。オメェの身体は俺の方が知ってるんだよ」
「彼氏面しないでくだせェ」
「うっせぇ、それより中に指入るか?」
沖田はうぇ、と変な声を出しながら探った。
「入れたかないですが多分入りやす」
嫌そうにしている様子が目に見えるようでつい土方は笑いそうになってしまう。基本的に性行為に淡泊な沖田は例えヒートであっても、自分から熱を発散することにあまり積極的ではないのは番になってから知った。番になるまでのヒートはどうやって対処していたのだと思うほど、土方に身を委ねていたのだ。身体を重ねるうちにこんな気持ちいいこと知らないとまで言わせることに成功したし、だからこそ一緒にできない今はその熱を自分で処理できず渋々土方の言うことに従っているのだろう。
「第二関節まで指入れて腹側の方にシコリがあるんだけどそこ触ってみろ」
「土方さん、第二関節ってどこですかィ? 肘?」
「え、マジで言ってる? どっから数えてんのそれ!?」
「冗談でさァ」
沖田が恐る恐る指を入れて動かすと確かにシコリがある。言われた通りに押してみると身体が跳ねた。
「んっ!」
「そう、そこ」
反応を土方が察したのが腹立たしく、沖田はキュッと唇を噛んだがそれすらもお見通しだった。
「ちゃんと声だせ。じゃないと良いかどうかわからねぇんだよ」
「こっちばっかりシてんのが割に合わないですが」
「俺もお前の声しか聞けなくて残念なんだ、我慢しろよ。爪立てるなよ、指の腹で最初はゆっくり……俺がやってるように」
「っ……ンッ、あっ」
「そう、少し激しく。膨らんで来てる」
触られていないはずなのに、あたかも触っているかのように言われるのが徐々に沖田を高めていく。
「やっ……土方、さん」
「ああ、いいぞ」
「あっあっあ――!」
左手で握っていた携帯を放って沖田は身体を振るわせた。合わせてビュッと多量の水分があふれだしてきた。
マイクが拾う、かすかな荒い息遣いを聞きながら土方は自分の下半身を激しく刺激する。
「ふっ……」
「土方さんもそろそろですかィ?」
最大限まで硬くなったところで息を整えた沖田が携帯を拾ったようだ。どうやら一度イってその気になったのか、スピーカーフォンにしてある。
「じぁあ俺もそろそろ挿れまさァ。土方さんどの張型がお好みで?」
「おい待て! まだ挿れんな! 潮吹いたあとは愛液が流れちゃってるからローション足しとけ!!」
そのまま挿入しそうな勢いだったため土方は慌てて静止の声をかける。案の定沖田はめんどくさそうな返事をする。
「へいわかりやした……うわっ冷た! このローション冷感でさァ。いつものじゃねェや」
「んなわけあるかよ」
「だって土方さんとしてる時こんな冷たいことないですよ、絶対メーカー違いやすって」
「こだわって買ってねェからいつもメーカーバラバラだっつうの。ローションは手であっためてから使わないと冷たく感じるもんなんだよ」
へぇ、と頷きかけて沖田は気がつく。土方はヒートの後半になるにつれてローションを使用することが多い。発情の熱に浮かされている沖田は細かいことは気にしていなかったが、それでも一度たりともローションの冷たさを感じたことはなかったように思う。
「土方さん……もしかして今までずっとそうしてやしたか?」
「まぁな……なんでちょっとキレてるんだよ」
土方が察した通り、沖田は急速に機嫌を損ねていた。
「だって俺が土方さんに夢中になってても、アンタはそういうことする余裕があったんだなって思っただけでさァ」
「こっちだって夢中になってるわボケ!」
沖田の感性はいつもずれているように土方は思う。そこは大事にされていると気が付いて欲しいところだというのに。
そんなことを言い合いながらも沖田はローションを中まで入れたようで、また小刻みに喘ぎ声を漏らしている。
「んっんっんっ」
「もうそろそろ入るな……」
頃合いをみて土方が声を掛ける。張型はカラクリ式ではない小ぶりの物を選ばせた。
「挿れるぞ、総悟」
「……へィ」
ゆっくりと沖田が張型を押し込むのに合わせて、土方も自身をゆっくり強めに握った。
「っ……」
「くっ、土方さん、全部入っちまいやした」
「ああ、動くぞ」
電話で繋がっているとはいえそれぞれ自慰をしているだけではあるのだが、タイミングを合わせると一人でするよりははるかに上回る気持ちよさを感じた。
「あっあっあんっ……!」
沖田も自身の気分をあげるためか、声を出して感じている。それは良いことなのだが、土方の受話器にカサカサとなぜか衣擦れの音が妙に響いてくる。
「ん? ちょっとまて総悟、何の音だ」
問いかけると沖田は無言になってしまった。
「……総悟?」
「……終兄さんが持ってきてくれた荷物でさ」
「まだなんかあったのかよ。何があんだよ、言ってくれねぇとお前をちゃんと抱けねぇ」
「道具じゃないんでお気になさらず」
頑なになって教えないのが更に怪しい。
「総悟、教えろ」
「……土方さんの隊服でさァ。新しくなる前のデザインのやつ。これあると落ち着くんでさァ」
「それって、お前……」
いわゆる巣作りなんじゃないかと言いたかったが、指摘すると止められそうだと思って言葉を切った。恐らく沖田は無意識にしているのだろう。不自然に終わった土方の言葉に沖田は慌てて弁明する。
「ちゃんと洗って返しやす!」
「ん、帰るまで使わねぇからそのまま持っとけ」
落書きはするなよと念押しだけする。死ねと書かれた隊服のことは、土方にとって色々な意味で忘れられない思い出だった。
「次会うときはこっちの隊服着たいですねィ」
「……そうだな。それより総悟、お前の中に出してもいいか?」
「あらら土方さんもうですか?」
情緒もなにもないですねと言った沖田に、土方は開き直って答えた。
「そうだよ、ずっと我慢してるんだからしかたねェだろ」
「……?」
ヒート以外でセックスをしたことはないので、いつもと変わらない頻度ではあるはずだ。沖田の疑問に、土方は自嘲した。
「いつでも抱ける距離にお前が居ないのが堪えてるんだよ、わりぃかよ」
「……悪く、は、ないでさァ」
「ほらいくぞ」
土方が言って、二人は再び手をそれぞれ動かした。
「っう……やぁ……あっあっ土方さん、きもち……」
「ああ、総悟、総悟……!」
「んんん――ッ!」
電話越しであるにも関わらず、二人は同じタイミングで絶頂を迎えることができた。
◇
「……ヒートの具合はどうだ」
「まだ続いてやすけど……とりあえず今日はこのまま寝れそうなくらいには落ち着てまさァ」
「明日は夜まで仕事抜けられないんだが……」
申し訳なさそうに申告した土方に沖田はドン引きして答える。
「冗談! あんなんは一回で充分でさ。あとは一人でなんとかしやす」
コツもつかめたし、と沖田は少し笑った。
今回使用しなかった方の張型をカタカタと揺らしながら、沖田はふと思う。
「カラクリがどんなに発展しても、まだピンク色のどこでも行けちゃうドアは作れねェんですねィ」
「……そうだな」
スレスレのセリフだが、沖田最大限の「会いたい」に土方が嬉しく思ったのも束の間のこと。
「……よく考えたら電話で声だけ飛んでくるっておかしくねェですか? 身体ごと飛んでこいよ土方ァ」
「おかしくはないだろ、無茶言うな馬鹿野郎!」
とんでもない無理難題をふっかけられてしまった。
「……次のヒートん時は戻れるようにするから」
改めてそういえば、沖田はこれ見よがしに溜息を吐いた。
「バカいっちゃいけねェや土方さん。次は旦那連れて『帰って』来てくだせェ」
一時的に戻ってくるなんていらない。一刻も早く、少しでも早く、この町の皆んなに日常が必要だった。
「アンタの代わりに汚れ仕事請け負うのは俺でも務まりまさァ。アンタは誰の代わりにもなれない光を見つけてきてくだせェ」
真選組の解散に当たって幹部でただ一人、真っ直ぐ苦言を申した沖田ももう前を向いている。しかしそれはそれで寂しさを感じて土方はついらしくもないことを口走る。
「だがお前の番の代わりは誰もいないだろう」
「それは土方さんが勝手にうなじ噛んだからですよねィ」
「……まだそれ言う?」
最初のセックスで噛みついてしまったことを、沖田は度々口にする。最初こそ毎回申し訳ないと思っていた土方も、隙あらば指摘されることに若干げんなりとしてしまう。それもお見通しのようで沖田はフッと笑った。
「冗談です、まあ助かってるんで」
「ならよかったよ」
土方は事後にゆっくりと会話するのは初めてかもしれないなと気が付く。ヒートを伴うセックスは大体沖田に負担が大きくすぐに寝落ちてしまい、そして起きたらまた行為を再開するという繰り返しだった。
「後処理終わったか? そろそろ寝とけ」
「……へィ、おやすみなせぇ」
土方はテレフォンセックスの間、沖田の表情が分からないことなどなかったのに今この瞬間の顔がわからなかった。
「……おやすみ」
やっぱり会いたいなと、口にすることはどちらもできないで通話が切れた。通話終了ボタンを押したのはほぼ同時。